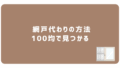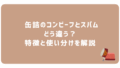卒業証書の筒を捨てるか迷ったときは、「使う場面があるかどうか」と「他の保管方法があるか」がカギになります。
賞状筒の分別は自治体ルールにより異なり、紙製・プラスチック製・金属製で処分方法が変わることも。
卒業証書の台紙だけを残して筒を手放す方法や、写真での記録、リメイクや再利用といった選択肢もあります。
収納を見直すきっかけにもなりますよ。
捨てる?残す?卒業証書の筒を手放す判断基準

使う場面を想定して考える
卒業証書の筒、日常で使うことはあまりないかもしれませんね。
とはいえ、たとえば転職時に学歴を証明する必要が出てきたり、資格の申請などで卒業証書が必要になることも。
そうした場面では、中身の証書があれば足りるケースが多いですが、念のために確認しておくと安心です。
筒そのものが必要になることは少ないものの、念のために数年保管しておく人もいるようです。
「思い出」か「モノ」か、見極めのヒント
なんとなく捨てにくい──それが卒業証書の筒の“あるある”ですね。
でも、その理由が「思い出として大切」なのか、「ただ何となく置いてあるだけ」なのか、自分の気持ちを確認してみると整理しやすくなります。
たとえば、筒を見ることで卒業式の場面がよみがえるなら、それは残す理由になるかもしれません。
逆に存在すら忘れていたなら、手放すタイミングかも。
後悔を減らすためのマイルールのヒント
「捨てたあとで気になるかも…」という不安、ありますよね。
そんなときは自分だけのルールをひとつ決めておくと、気持ちの整理がつきやすくなります。
たとえば、こんな方法があります:
- 筒の写真を撮ってから処分する
- 一度まとめて箱に入れ、1年間使わなかったら見直す
- 家族に見せたあとに手放すタイミングを決める
「捨てる」ことが目的ではなく、「納得して選ぶ」ことが大切なんだと思います。
そうすれば、どんな選択でも自分の中で整理しやすくなりますよ。
筒がかさばって邪魔…収納スペースを確保する方法

省スペースにつながる収納アイデア
卒業証書の筒って、何本もあると意外と場所を取るんですよね。
しかも長くて丸いから、棚の中でも転がるし、立てても倒れるしで、ちょっと扱いづらい存在です。
そんなときは、筒の特性に合わせた収納法を試してみるとスッキリします。
たとえば:
- クローゼットのすき間に立てて入れる
- ケース付きの書類ボックスに横向きでまとめる
- 押し入れの隅に束ねて収納する
無理に詰め込まず、スペースに合った方法を選ぶことで、収納のムダも減らせますよ。
複数本あるときの整理の工夫
小学校から大学、さらには資格講座などで、いつの間にか賞状筒が増えていた…なんてこともあるかもしれませんね。
それぞれに思い出があって、手放すのも難しい。
でも、全部取っておくのは現実的じゃないですよね。
そんなときは:
- 中身だけを取り出して、筒は処分する
- 卒業証書専用のファイルにまとめる
- 代表的な1本だけを記念に残す
「思い出は残したいけど、場所はとりたくない」という人には、収納の見直しがちょうどいいタイミングかもしれません。
見せる収納?隠す収納?スタイル別の選び方
捨てるのはちょっと…という人は、“見せる収納”という選択肢もあります。
たとえば、デザインの凝った筒なら、棚の上に飾るだけでちょっとしたインテリアになりますよ。
一方で「とにかく見えないところにしまいたい」という人は、ベッド下やクローゼットの高い位置など、視界に入らない場所を活用するのが◎。
どちらを選ぶにしても、「自分が気にならない収納」が1番です。

暮らしに合った形を見つけて、気持ちのスペースも一緒に空けていきたいですね。
スッキリしたい人必見!卒業証書と筒の整理術

「保管」「処分」「移行」の3つの視点で考える
卒業証書やその筒をどうするか、悩んだときは「保管」「処分」「移行」という3つの視点で整理するとスムーズです。
たとえば──
- 保管:原本を大切に保存しておきたい場合。防湿性のあるケースや書類ファイルの利用も◎
- 処分:筒だけ手放す、中身もまとめて処分するなど
- 移行:デジタル化や写真で残して原本を整理するやり方
こう考えると、「捨てるか残すか」だけでなく、“持ち方を変える”という選択肢も見えてきます。
スッキリするための第一歩は、こうした視点の切り替えかもしれません。
家族と共有する思い出整理のタイミング
卒業証書って、自分の節目を記録したものではあるけれど、家族と一緒に振り返るきっかけにもなります。
子どもに見せると、「パパも昔は学生だったんだね」なんて、ちょっとした話のネタになったり。
おすすめのタイミングは:
- 引っ越し前の整理中
- 季節の衣替え時
- 子どもの入学・卒業といった節目
思い出って、片づけながら共有するとちょうどいい距離感になりますね。
卒業証書のデジタル保存という選択肢
最近では「物を持たない暮らし」を選ぶ人も増えていて、証書類もデジタル保存が注目されています。
スマホで撮影して、クラウドやフォルダで管理するだけでも、かなりスッキリします。
メリットは:
- 保管場所を取らない
- 劣化や紛失の心配が少ない
- 必要なときにすぐ取り出せる
もちろん、正式な証明が必要な場合は原本が求められることもあるので、状況に応じて使い分けるのが現実的です。
写真だけでも気持ちはしっかり残せる、そんな柔軟さも今の時代っぽいですね。
卒業証書の筒、リメイクや再利用のアイデア集

小物入れやペン立てなどへのアレンジ例
「卒業証書の筒、なんだか捨てにくい…」と思ったら、再利用してみるのもひとつの手です。
しっかりした素材と筒形という特徴を活かせば、ちょっとした収納グッズに変身します。
アイデアの例:
- ペン立てや文具入れにカットして使う
- 乾電池やケーブルの一時保管容器に
- キッチンでラップの芯や割り箸の収納用にも応用可
塗装したり、マスキングテープでデコレーションすれば、部屋になじむ雰囲気にもなります。
ちょっとしたDIY感覚で楽しめるのも魅力ですね。
子どもと一緒に楽しむクラフト活用
「これ、ママ(パパ)の卒業証書が入ってたやつだよ」と話しながら、筒を使ってクラフト遊び。
意外と盛り上がります。子どもと一緒に楽しめる工作素材として、賞状筒はちょうどいいサイズ感なんです。
こんな使い方があります:
- 望遠鏡ごっこや剣の小道具に
- 夏休みの自由研究の素材に
- 季節の飾りやリースの土台に
大げさな材料も道具もいらないので、思いついたときにすぐ取りかかれるのもポイント。
家に眠らせておくよりも、使って笑える時間のほうが価値があるかもしれません。
リメイク前に知っておきたい準備と注意点
リメイクする前に、ちょっとだけ確認しておきたいこともあります。
というのも、素材によっては加工しづらいことがあったり、ケガのリスクがあったりするからです。
チェックポイント:
- 中身をしっかり取り出してから作業する
- 切断する場合はカッターやハサミの扱いに注意
- 塗料や接着剤を使う場合は換気をしっかり
また、プラスチック製の筒は刃が滑りやすいこともあるので、ゆっくり丁寧に作業するのがコツです。
リメイクも安全第一で。楽しく活用するための準備として、ちょっとした注意を忘れずに。
卒業証書はどう保管する?筒を手放す前の代替策

台紙だけ保管する方法やケースの活用
卒業証書の中身は意外とフラット。そこで、筒を手放す前に「証書だけをどう保管するか」を見直してみると、収納がラクになります。
おすすめは、証書を傷めずに保管できるケースやファイルを活用する方法です。
使えるアイテム例:
- 厚紙タイプのクリアホルダー
- 卒業証書用の専用ファイル
- 書類ボックスにまとめて保管
封筒に入れておくだけだと折れやすいので、台紙のまま保管できるしっかりめのケースがあると安心ですね。
写真に残すスマートな記録方法
「手放したいけど、証拠として残しておきたい」そんなときにぴったりなのが写真保存。
スマホで撮ってクラウドやフォルダに整理しておけば、必要なときにすぐ見返せます。
撮るときのコツ:
- 照明の反射を避けて明るい場所で撮影
- 文字が読めるようにまっすぐ配置
- ファイル名に「学校名+年号」を入れておくと便利
原本の代わりにはならない場面もありますが、ちょっとした確認用としてはじゅうぶん役に立ちますよ。
保存に向いている場所と保管の工夫
卒業証書は紙なので、湿気や直射日光には弱いもの。
長期保管を考えるなら、置き場所や収納の仕方もちょっとだけ気にかけておきたいですね。
保管に向いた場所の例:
- クローゼット内の引き出し(高温多湿を避けられる)
- 書類用の収納ボックスに横向きで保管
- 防湿シートを一緒に入れておく
見た目がスッキリするだけでなく、証書の劣化も防ぎやすくなります。
せっかく残すなら、なるべく良い状態で保っておきたいところです。
処分してから気づくことも?必要性の整理方法

就職・転職などで求められるケース
卒業証書って、日常生活ではあまり登場しませんが、いざというときに「あれ、どこに置いたっけ?」となりがちです。
特に必要になるのは、次のような場面です。
- 国家資格や免許の申請時
- 海外留学やビザの手続き
- 転職や再就職で学歴証明が求められるとき
もちろん、再発行できる学校もありますが、手続きや日数がかかることもあるので、原本を保管しておくと安心材料になります。
「いらない」と思っても保管する選択肢
「もう使わないし…」と思って手放したくなることもありますが、ちょっと待ってみてもいいかもしれません。
ライフステージが変わると、「取っておいてよかった」と感じる場面もあるからです。
たとえば:
- 子どもが進学するタイミングで話のタネになる
- 自分の歴史を見つめ直したくなったときの記録になる
- 実家にまとめて保管することでスペースを確保できる
保管方法さえ見直せば、それほど邪魔にもならないこともあります。
不要かどうかは「今」の基準だけで決めず、少し先の未来を想像してみるのもアリですね。
処分した人の声から学ぶ判断のヒント
実際に「捨ててスッキリした」という人もいれば、「あのとき手元に残しておけば…」とちょっと引っかかっている人もいます。
SNSやネット掲示板をのぞいてみると、さまざまな本音が飛び交っています。
よく見かける声:
- 「思いきって処分したら、部屋が片づいた」
- 「手放したあと、証明書の提出を求められて焦った」
- 「写真に残してから捨てたので気持ちがラクだった」
このように、どちらにもメリット・デメリットがあるので、自分の状況に照らし合わせて選ぶのが良さそうですね。
「今は使わないけど、将来どうなるかな?」という視点を持つことで、納得のいく判断につながります。
まとめ
卒業証書の筒を捨てるかどうかって、意外と悩ましい問題なんですよね。
見た目はただの筒でも、中には思い出やちょっとした役割が詰まっていたりします。
とはいえ、すべてを取っておく必要はありません。
使う予定があるのか、収納スペースをどう使いたいのか、写真で残すのか——それぞれの選択肢を知ることで、スッキリとした気持ちになれるものです。
「なんとなく残してた」が「ちゃんと考えて選んだ」に変わるだけで、ぐっと身軽になりますよ。